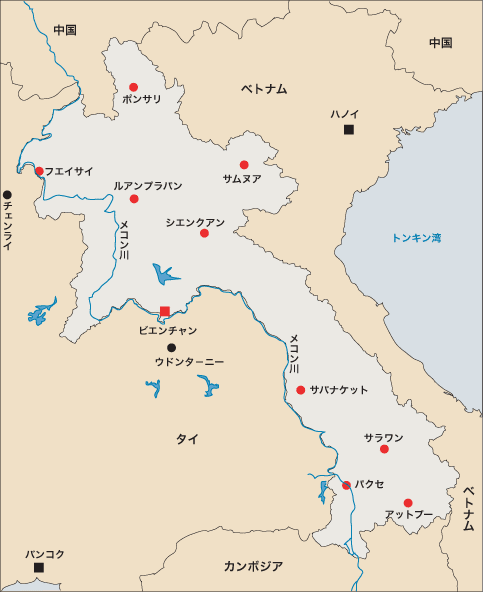| 国名 | ラオス人民民主共和国(Lao People's Democratic Republic) |
| 面積 | 23万6,800平方km(本州の約1.04倍) |
| 人口 | 636万8,162人 (2010年推計) |
| 首都 | ビエンチャン |
| 言語 | ラオ語(公用語) |
| 宗教 | 仏教 |
| 通貨 | キップ 1 new kip (NK) = 100 at |
| 為替レート | 1ドル=約7,700キップ 100キップ=約1.38円 |
| 日本との時差 | -2時間 |
| ビザ |
※ビザやパスポートなどの情報は予告なく変更されることがあります。 必ず、ラオス大使館、領事館などで確認してください。 |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
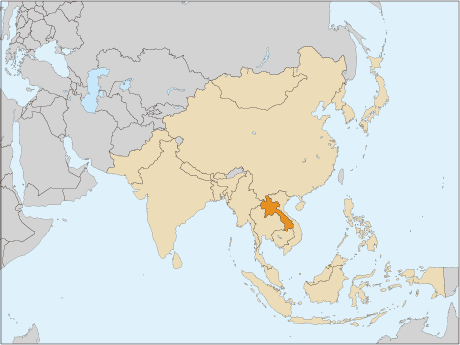
- 位置:タイの北。
- 国土の面積
- 全面積: 236,800平方km
- 陸地の面積:230,800 平方 km
- 国際紛争:タイとの間に国境紛争。
- 気候: 熱帯性モンスーン気候。 雨期(5月から11月)、乾期(12月から4月)
ビエンチャンの気温・降水量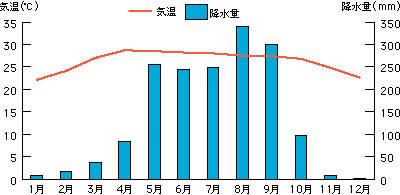
- 地形:大部分は険しい山。平地や高原がいくつかある。
- 天然資源:スズ、水力、石膏、木材、金、宝石
- 気候: 熱帯性モンスーン気候。 雨期(5月から11月)、乾期(12月から4月)
- 正式名称:ラオス人民民主共和国
(英語:Lao People's Democratic Republic/ラオ語: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao)- 政体:共産主義
- 首都:ビエンチャン
- 独立:1949年7月19日 (フランスから)
- 憲法:1991年8月14日公布
- 投票権:18歳以上の国民すべて
- 行政府
- 政体:共産主義
- 元首: チュンマリー・サイニャソーン国家主席(ラオス人民革命党書記長) (2006年6月より)
- 政府の長:首相 ブアソーン・ブッパーヴァン(党政治局員) (2006年6月より)
- 立法府:1院制
- 国民議会:議席数99。最新の選挙は2002年2月に行われた。(次回選挙は2011年)
- 政党および指導者
- ラオス人民革命党 (LPRP)、党首チュンマリー・サイニャソーン
- 他の政党は禁止されている。
- 他の政治・圧力団体
- 共産主義団体以外は禁止されている。大部分の反対勢力の指導者たちは、1975年に国外へ脱出した。
- 国旗:3つの水平な帯。上から赤。青(2倍の幅)、赤。青の帯の真ん中に大きな白い円がある。
- 1997年7月23日、ラオスはミャンマー(ビルマ)とともにASEANに正式加盟した。
■軍事
- 軍事費:1億0500万ドル、 GDPの 8.1% (92/93年)
- 概況:数少ない共産主義国家の一つであるラオスは、1986年から中央管理経済をやめ、民営企業を支援している。その結果、極端な低いベースから始まった成長は、1988〜96年の成長率は、平均年7%を続けた。
ラオスの貿易はほとんどをタイに頼っている。そのため、1997年のタイの金融危機の影響を被り、成長率はほぼ1.5%に落ちた。
ラオスは陸地で囲まれておりインフラはあまり整備されていない。鉄道はなく道路網も整備されていない。そして国外国内への通信網もわずかである。電気は、いくつかの都市部にしか供給できない。
農業は自給のために営まれているが、GDPの半分を占め、雇用全体の80%を占めている。主要作物は米である。
旱魃のない年には、ラオスは全般的に食料の自給ができる。しかし、洪水や害虫、局地的な旱魃は、国のさまざまな地域でおいて欠乏を引き起こす。
予見する限りでは、ラオスの経済は IMFや他の国際的な方面からの援助に頼らざるを得ないようだ。日本はラオスに対する最大の援助国である。 旧ソ連や東ヨーロッパからの援助は、その崩壊により突然になくなった。
多くの開発途上国のように、山林伐採と土壌侵食により、高いGDP成長率を取り戻すのは困難になるだろう。- GDP(MER): 55億9,800万ドル (2009年:IMF)
- 一人当たりGDP(MER):877.968ドル (2009年:IMF)
- GDP(PPP): 144億4,700万ドル (2009年:IMF)
- 一人当たりGDP(PPP):2,265.996ドル (2009年:IMF)
- 国内総生産実質成長率:7.590% (2009年:IMF)
- インフレ率(消費者物価):3.920% (2009年:IMF)
- 失業率:4.5% (1995年推計)
- 国家予算(1997年推計)
- インフレ率(消費者物価):3.920% (2009年:IMF)
- 歳入:2億3020万ドル
- 歳出:3億6590万ドル
- 輸出:3億131万ドル (1996年推計)
- 商品:木工品、コーヒー、電気、スズ、衣服
- 相手国:ベトナム、タイ、ドイツ、フランス
- 輸入:6億7800万ドル (1996年推計)
- 商品: 食料、燃料油、消費財、工業製品
- 相手国:タイ、日本、中国、シンガポール
- 電力:
- 発電量:12億 kWh
- 一人当たり消費量:60 kWh (1995年推計)
- 産業:スズおよび石膏採鉱、電力、農産品加工、建設
- 農業:
- 主要作物-米 (耕作地の80%)、さつまいも、野菜、トウモロコシ、コーヒー、サトウキビ、
- 家畜:水牛、ブタ、牛、鶏
- 麻薬:国際的な麻薬取り引きのための大麻や阿片用のケシの生産地。世界第4位のアヘン生産地(1994年には85トン)。ビルマで作られたヘロインの積み替え地としてますます使われている。
- 通貨:キップ
- 1 new kip (NK) = 100 at
- 為替レート:1ドル=キップ- 2,500 (1998年)、1,256.73 (1997年)、921.14 (1996年)、 804.69 (1995年)、717 (1994年)、 720 (1993年7月)、710 (1992年5月)、 710 (1991年12月)、700 (1990年9月)、 576 (1989年)
- 1995年9月、変動相場制に移行した。
-
交通・運輸
- 鉄道: 0 km
- 幹線道路:
- 鉄道: 0 km
- 全長:22,321 km
- 舗装: 3,502 km
- 未舗装: 18,819 km (1997年推計)
- 舗装: 3,502 km
-
通信
- 電話:19,333回線 (1996年推計)
- ラジオ局: AM 10、 FM 0、短波 0
- ラジオ台数: 56万台(1992年推計)
- テレビ局: 2
- テレビ台数: 3万2000台(1993年推計)
- 電話:19,333回線 (1996年推計)
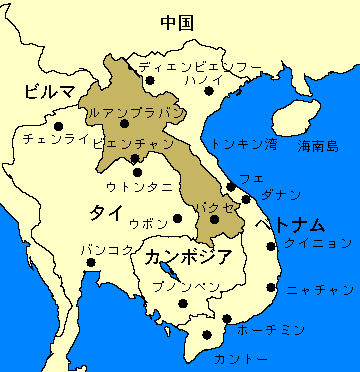
- ■〜19世紀
- ラオスの地は長く、タイ人(シャン族、シャム族、ラオ族を含む)の移住者とモン族、ミエン族などの高地民族によって支配されていた。 最初のラオスの公国はフビライ・ハーンによる中国南西部の侵略の後、13世紀に確立された。
14世紀中頃、クメールに支援された将軍ファ・グンが、ルアン・プラバン周辺に散在する公国を併合して王国を樹立した。ランサン王国(Lan Xangは100万の象という意味)である。
ランサン王国は、最初繁栄していた。しかし内部分裂と隣国からの圧力で17世紀、ルアン・プラバン、現在のビエンチャン、チャンパサクをそれぞれ中心とする3つの王国に分裂した。
18世紀後半には、ラオスの大部分はタイの支配下にあった。しかしまたベトナムの圧力も強かった。
1820年代にラオスはシャムに対して戦争を行った。この戦争でラオスは敗れ、3つの王国全てがタイの支配下に入った。
19世紀後半までには、ベトナムのトンキン、アンナン地域に、フランス領インドシナが作られた。
タイは結局フランスにラオス全てを譲渡した。フランスは単に植民地とシャムの間の緩衝器としてその領土を使うことで満足した。 - ■20世紀
- 第二次世界大戦中、日本軍がインドシナ半島を占領した。
戦後、ラオスのレジスタンスグループ、ラオ・イサラ(Lao Issara/自由ラオス)は臨時政府をビエンチャンに樹立したが、1946年フランス軍によって制圧され、ラオスはフランス領に戻った。
1949年、ラオス王国はフランスの勢力下で、独立国となった。
1950年、スファヌボンらによりネオ・ラオ・イサラ(自由ラオス戦線)が結成され、対フランス闘争を行った。
1953年10月22日、ラオス王国の完全独立は達成された。しかし王党派、中立主義者と共産党の闘争が始まった。
ネオ・ラオ・イサラは、パテト・ラオ(ラオス愛国戦線)と名前を変更した。
1957年、政府とパテト・ラオは連合政府を樹立した。
1958年、新しく親米派サナニコンによる政権ができた。サナニコン政権はパテト・ラオを弾圧し、政府とパテト・ラオとの内戦が始まった。
1960年、中立派のプーマによる政権が樹立されたが、左、右、中立3派に分裂した。
1962年、3派連合政府ができたが、翌63年、内戦が再開した。
ビエンチャン王党派とパテト・ラオとの戦闘は激しくなっていった。パテト・ラオは北ベトナムと協力していた。そのためベトナム戦争でアメリカは、1964年ラオス東部のホーチミンルートの攻撃を始めた。
1973年になると停戦協議が行われた。
1974年4月、連立政府が樹立された。しかし1975年、ベトナムでサイゴンが陥落すると、大部分の王党派はフランスへ亡命した。
パテト・ラオは,平和的に権力を掌握し、ラオス人民民主共和国が1975年11月建国された。
1975年以来、政府は企業を国営化し,私営企業は閉鎖されていたが、1989年、その規制を緩和し、小規模ではあるが、市場経済へ移行している。
- 人口:636万8,162人 (2010年推計)
- 人口構成(1998年推計)
年齢 構成比 女性 男性 0-14 歳 45% 117万4,323人 125万5,210人 15-64 歳 52% 139万3386人 131万8,061人 65 歳以上 3% 9万2,474人 7万7,388人 - 人口増加率: 2.76% (1998年推計)
- 出生率:1,000人当たり40.58 人(1998年推計)
- 死亡率:1,000人当たり12.97 人 (1998年推計)
- 乳幼児死亡率(1歳以下):出生1,000人当たり 91.81人 (1998年推計)
- 平均寿命 (1998年推計)
全人口平均 男性 女性 53.7歳 52.13歳 55.34歳 - 民族構成:ラオ族 Lao Loum (低地) 68%、ラオ族 Lao Theung (高地) 22%、 ラオ族Lao Soung(山地/ モン族(メオ族) およびヤオ族 (Mien)を含む) 9%、 ベトナム・中国系1%
- 宗教:仏教 60%、アニミズムその他40%
- 言語:ラオ語(公用語)、フランス語、英語、さまざまな少数民族の言語
- 識字率(15歳以上) (1995年推計)
全人口平均 男性 女性 56.6% 693.4% 44.4% - 労働力:100〜150万人
- 職業: 農業 80% (1997年推計)
- 人口構成(1998年推計)